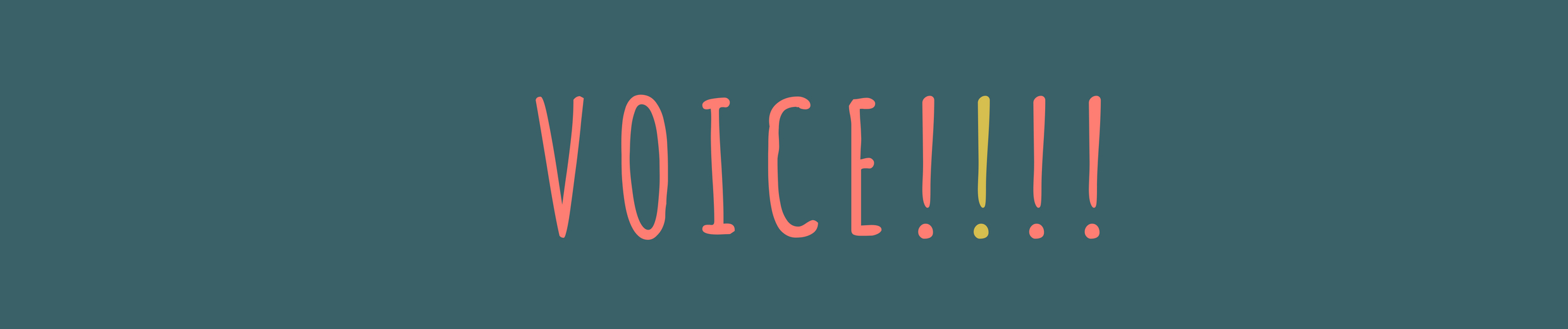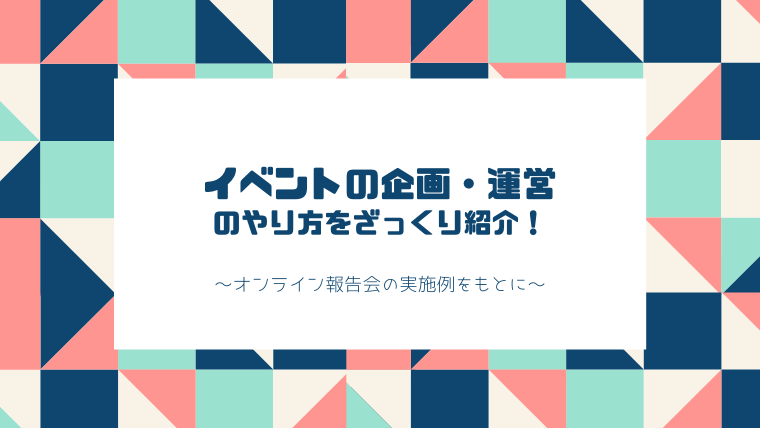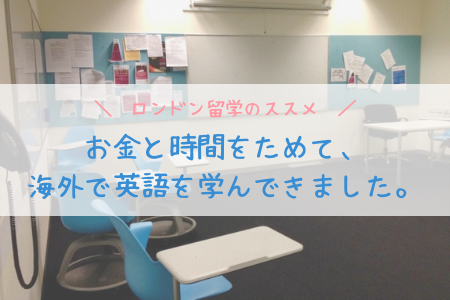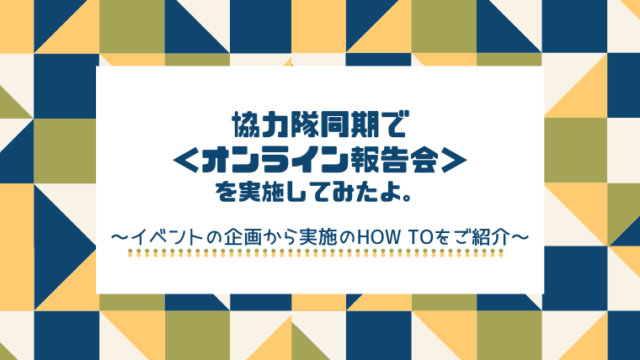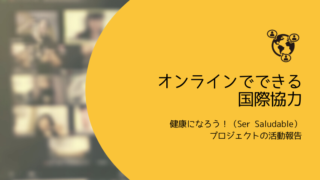この記事では、イベントの企画や運営のやり方について、ざっくりとご紹介します。
JICA海外協力隊として一時帰国中ですが、この度同期を招集してオンライン報告会を実施しました。
イベントの企画運営にあたって、どうやればいいかわからない方、苦手な方も、少し工夫するだけで簡単に参加者に楽しんでもらえるイベントを実施することができます。
今回は私が実施したオンライン報告会を例に、イベントを作成するときの私の着眼点、注意点を交えながらやり方をざっくりとご紹介しようと思います!
実施したオンライン報告会の概要
JICA海外協力隊で一時帰国している同期隊員を対象にオンラインで報告会を実施。
発表者・傍聴者ともに希望者を募り、日程を決めてzoomを使用した。
いつ(日時):5月末、6月上旬の土日の午後
どこで(実施場所):zoomを使用したオンライン上で
だれが(参加者):同期隊員40名(うち発表者14名)
なにを(内容):JICA海外協力隊としての派遣国での経験。一人当たり質疑応答を含め30分
なぜ(目的):同期の活動や生活を知ったり、スピーカーの経験値へとつなげるため
どのように(やり方):zoomの画面共有等を使用した発表形態。コメントや質問はzoomのチャット機能を利用する
このように、同期でオンライン報告会を実施しました。
イベントの企画・運営の流れを確認しよう
イベントを行う時に、まずどこから始めるのか。
イベントは発案から実施までいろんな流れがありますが、こちらではざっくりとそれをご紹介します。
- イベントの発案:こういうのやりたい!というやつです。
- イベントの企画:どんなイベントをやるのかを考えます。
- イベントの案内:こういうのやります!と参加者を募ります。
- イベント実施までの準備:参加者や内容を詰めていきます。
- イベントの実施:実際にイベントを実施します。
- イベントのフィードバック:実施したイベントのフィードバックをもらいます。
ざっくりとこんな感じの流れになります。
それでは個別にやり方をご紹介します。
イベントの発案と企画
まずはイベントの発案。
こんなのがやりたい!というのが思いついたら実際に企画をしてみましょう。
このときに5W1Hを意識して企画ができると進めやすいですし、実際にイベントの案内をするときに参加者も理解しやすい内容となります。
5W1H(When, Where, Who, What, Why, How)
いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのように行うのか。
これは企画段階で全て完全に決まっている場合が多いですが、
参加者と一緒に企画を作っていく場合であれば柔軟性を持たせるため未決定でも大丈夫です。
未決定の場合は何が未決定でそれをどのようにいつ決めたいのかもはっきりさせましょう。
例えば、今回のオンライン報告会では
あらかじめ「どこで」「なぜ」「どのように」は決まっていました。
「オンラインで」「同期の活動を知ったりスピーカーの経験値をあげる」「zoomの画面共有等をもちいる」です。
一方で、「いつ」「だれが」「なにを」は決まっていませんでした。
なぜならいずれも参加者の都合で決めたかったからです。
そこはあえて完全に固定せず融通性を持たせました。
この時融通性を持たせずにきっちり全部決めると楽ではありますが、参加者の全体は減ります。融通性を持たせると参加希望者は集まりやすいですが、そのあとの準備などが結構大変になります。
イベントの案内
イベントの案内は、先ほどの企画案をまとめて参加者を募るために行います。
内容は参加者が過不足なくそのイベントを知り、参加したい場合はどのように参加することができるかを案内したものとなります。
大規模なイベントになるとこの案内から参加者を募るまでがとっても労力がいると思うので、フォームに入力してもらう、参加者名簿を作成してみる、など工夫があると良いでしょう。
この案内をするときに、なるべくどのようなイベントを行おうとしていて、どこが決まっていてどこが決まっていないのか、わかりやすく案内することが大切です。
なぜなら、
たとえばもらったイベントの詳細が不明瞭な時あなたならどうしますか?
質問するか、不明瞭のためよくわかんないし参加しなくていいやとなりますよね。
わからないところは質問してもらえるといいのですが、質問をするほどでもない場合は、よくわかんないからという理由で放置されます。
最初からある程度分かりやすいイベントの内容を案内することで、参加者を募りやすいのです。
私は下記のようなぱっと見れるフライヤーのようなものを作り、一つの画像にしてLINEに貼り共有してもらいました。
この時、相手の労力を煩わせ集客するために見やすく、開きやすく、わかりやすいものを作ると良いでしょう。
Wordにせずにそれをクリックしたら内容が読めるようにしたのは、そういう工夫があるためです。
 ↑実際に使用した報告会のフライヤー
↑実際に使用した報告会のフライヤー
イベント実施までの準備
案内をしたのちに、参加希望の連絡が入ると思うので、それと並行してイベントの準備を進めましょう。
具体的には日程の調整、場所の準備、参加者への通知、内容の精査等です。
今回はオンライン報告会をベースにイベントを行うことを紹介しているので、その準備内容等を共有します。
- 発表者LINEを作成し、発表希望者に参加してもらう
このLINEでは発表者のみが参加するので、発表日のスケジュール調整や連絡事項の共有、どういう内容で進めていくかを共有します。
- 発表者に向けて指示を出す
どういう形態の発表を行うべきか、時間や内容などを指示します。これは先ほどの全体案内よりももっと詳細な内容を提示し、発表者が混乱しないように工夫します。
発表すべき内容が不明瞭、何のためのイベントなのか、どれくらいの時間が使用できるのか、などがわからないと発表者もどういう内容で準備すればいいのかわからないのでそこは気遣いポイントとなります。
(今回のオンライン報告会では一人ひとりに「私の一枚」を紹介してもらうことを統一ルールとし、発表の内容は派遣国でのことであれば問わないことにしました)
- 発表者と個別でも内容を詰める
発表者の個人的な質問やアドバイスなどに対応します。
- 参加者全体LINEを作成する
このLINEは発表者も含む参加希望者全体が参加します。
報告会実施の際zoomを使用してどのような流れで行うのか、注意事項をまず共有しあらかじめイメージを持ってもらいます。
日程が決まり次第案内し、また当日のプログラムも作成したら共有しましょう。
このLINE当日の報告会でも使用することになります。
イベントの実施
さて、発表者と主催者の準備が整ったらいよいよ実施です。
可能であれば前日~当日の30分前に参加者全体にリマインドをしましょう。オンラインでないイベントの場合は、数日前~前日にリマインドをしましょう。
場所の設定、受付を行い、イベントを実施します。
このとき、なるべく参加者に満足してもらえるようなイベント実施になるよう心がけましょう。
イベントにもよりますが、「スムーズさ」と「内容の濃さ」が求められることが多いです。内容の濃さは発表者やスピーカーの準備によるものになりますが、スムーズさは主催側の工夫が活きます。
たとえば参加者が迷わないように、休憩時間の設定、参加の仕方の事前共有、途中入退出等可能化の有無、質問コメントの受付等、どのように行えばいいのかをあらかじめ案内するなど、工夫があると良いでしょう。
イベントのフィードバック
イベントを行ってフィードバックをもらえたらもらいます。
Gooleファームなどを使用してアンケートを集めることもできますし、参加者から直接コメントをもらいましょう。
これをする意図は①参加者に積極的参加を意識してもらう、②今後のイベント企画運営に活かす、があります。
フィードバックを行うことをあらかじめお願いすることで集中して発表を聞いてくれたり発表者も感じたことをアウトプットする場が提供できます。
またPDCAサイクルを回すという意味でも発表者や主催者に対してフィードバックをもらうと今後どのような工夫ができるのか、どのような需要があるのかを知ることができ、次につなげられます。
今回私も初めてGooleフォームでアンケートを作りましたがとても簡単だったのでお勧めします!
ワードなどでアンケートを作るとLINEをパソコンにつないでいない人はメールでやり取りしないといけなく、その手間がフィードバックの収集率を落としてしまいます。Gooleフォームだとそのリンクでそのまま回答ができるので回答を集めやすく、参加者も回答しやすくなります。
Gooleフォームは、Gooleアカウントを持っている人は簡単に作れるのでチャレンジしてみてください。
イベントを実施した感想
今回ぱっと思いついてイベントを企画し、運営してみました。
基本ひとりで全部やったのですが、もっといろんな人に手伝ってもらえば?という声も多くもらいました。イベントを一つ企画し実施するとなると結構仕事量も多くなります。手伝ってくれる人がいたら手分けするのもアリだと思います!
また、参加者約40名(うち発表者14名)と同期全体の半分の人が参加をしてくれました。みんな同窓会気分でとっても楽しく参加してもらたようなのでやってよかったなと思います。
発表者からはフィードバックが良かったとコメントをもらいました。実際こういうのはやって終わりが多く発表者がフィードバックを受ける機会が少ないので、発表者に対しそういう形で今回のオンライン報告会で発表したことに付加価値が提供できたのは良かったと思います。
またZoomの利便性はとても高いと感じました。無料アカウントのため40分ごとで部屋を使い分けて行うことになり発表者ごとに部屋を分けて実施しましたが、逆にそれが良かったという声もありました。
最初は40分で部屋を分けるって大変なんじゃ…という声も上がったのですがやってみると逆に強制的に30分で発表をおえる必要が出てくるのでメリハリができてよかったという声があり、物は使いようだとおもいました。
他のイベントでも応用してみよう!
今回はオンライン報告会を例にとり紹介しましたが、ほかのイベントにもこの流れ、やり方で様々な企画・運営が可能です。
この記事ではざっくりと私のイベントの企画・運営方法をご紹介しましたが、さらに大規模なイベントになるとさらに準備が必要なこともあります。
時に応じて応用していってみてください!
オンライン報告会実施の報告をベースにイベント運営のHOW TO(ハウツー)を書きました。
あわせて参考にしてみてください!!!オンラインで何かやるときは要チェックです。